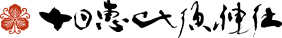えびす様と
だいこく様


御祭神
大國主大神
大國 さま

だいこく様は、事代主大神の父神様で
「大國主大神(おおくにぬしのおおかみ)」と申します。
だいこく様は「天の下造らしし大神」とも言われるように、私たちの遠い遠い親等と喜びも悲しみも共にせられて、国土を開拓され、国造り、村造りに御苦労なされて、この住み良い日本の国土を築き、豊葦原(とよあしはら)の瑞穂(みづほ)の国と呼ばれるような、あらゆるものが豊かに成長する国を造り上げられました。
そして農耕、漁業をすすめて人々の生活の基礎を固め、殖産の法をお教えになり、又医薬の道をお始めになって人々の病苦をお救いになるなど、慈愛ある御心を寄せられた救いの親神さまであると共に、すべてのものが自然の姿にあるように護って下さる神様です。この国造りの大業を成し遂げた後、日本民族の大親である
「天照皇大御神」に、その豊葦原の瑞穂の国をお譲りになりました。
だいこく様は、人が立派に成長するように、社会が明るく全てのものが幸福であるようにと、我々に愛情を限りなく注いで下さり、幸福の「縁」を結んで下さることから、「結びの神様」としてあまりにも有名です。
人と人、人と社会、人と幸福…さまざまな「縁」を結んでくださるだいこく様は、福の神として慕われ、広く深く信仰をおうけになっています。
事代主大神
恵比須 さま

えびす様は、「事代主大神(ことしろぬしのおおかみ)」と申します。お父様は「大國主大神(おおくにぬしおおかみ)」で、弟神には「天照大神(あまてらすおおかみ)」がいらっしゃいます。また、「須佐之男命(すさのおのみこと)」の御子孫でもあります。
事代主大神は父神「大國主大神」をお助けなされて国土の経営、産業福祉の開発におつくしになりました。
天孫降臨に先だち、使いの神が出雲にお下りになり、大國主大神に「この国を天つ神に献れ」とお伝えになった時、事代主大神は三保関で釣を楽しんでおいでになりましたが、父神のお尋ねに対し
「この国は天つ神の御子に奉り給へ」とお答えされ、父神はその御言葉通り国土を御奉献なされました。そして事代主大神様は多くの神々と共に皇孫を奉護し、日本建設に貢献なされました。
神武天皇、綏靖天皇、安寧天皇御三代の皇后様は事代主大神の子孫で、古来より宮中八神の御一柱として御尊崇のあつい神様です。また、事代主大神様は一名「えびす」様と申しまして、「だいこく」様と共に世の崇敬特に厚く、私達が最も信仰し、一番親しみのある神様です。釣竿を手にして鯛を抱かれた福徳円満の御神影はあまりにも有名です。人の世の日常の行為や行動を指導され、漁業の祖神海上安全、商売繁昌の守護神としての御霊験の広い事は極めて広く知られている通りです。そして大義平和の御神徳、産業福祉の道をお開きになった御神業、福徳の神と仰ぐ神様でもあります。

出雲からの縁結び

出雲のからの御分霊 結びの神だいこく様
十日恵比須神社のだいこく様は、今では貴重な出雲大社からの御分霊です。
現在、御分霊をいただく事は、出雲大社に限らず全国どこの神社も行っておらず大変珍しい事です。
十日恵比須神社で祀られているだいこく様は、縁結びの神様としてあまりにも有名であり、又福の神として慕われ広く深く信仰をおうけになっているのも人間が立派に成長するように、社会が明るく楽しいものであるようにすべてのものが幸福であるようにと、お互の発展のためのつながりがこの「むすび」の御神徳に依り結ばれる事であり、我々に愛情を限りなく注いで下され、人間の幸福の「縁」を結んで下さる神様であります。
当社には、えびす様(事代主大神)の父神、だいこく様(大國主大神)も一緒にお祀りしております。全国的にも非常に珍しく出雲大社から御分霊を迎えて合祀致しました。

十日恵比須神社の御由緒
「福岡懸神社誌」(昭和19年刊)によると、「香椎宮社家の武内平十郎(後隠居して五右衛門と称す)が博多に分家し、神屋と号して商売を営んだ。此の者天正十九年(一五九一年)正月三日、年始に当り香椎なる父の家に至り、香椎宮、筥崎宮への参詣の帰途、浜辺潮先に於て、恵比須大神の尊像を拾い上げたる地に御社を建て氏の神と家運大いに栄えたと云う」とあります。
また、「明治参拾参年旧正月記録ヨリ写取者也」と添え書きのある武内文書「十日恵比須神社記録写」には「香椎から箱崎に参拝途中の潮先で、恵比須二対を拾い上げて、持ち帰って奉斎した」「毎年正月十日恵比須ととなえて、自身でお供えして拾い上げたところで御神酒をささげた。これが知られて次第に参拝する人が多くなって繁昌した」という意味のことが書かれています。
当時、社は崇福寺境内にあったようですが、博多に分家した香椎宮ゆかりの武内家の一族が、最初は自宅に祀り、のち千代の松原に一社を建立したのが始まりらしいとのことです。
恵比須神社は本来、漁業と深い関係にありますが、どちらかというと十日恵比須神社は“商人色”が強いようです。漁業でも“流通”関係が目立っており、起源との関連をうかがわせます。

十日恵比須神社のはじまり
天正19年西暦1591年、武内家隠居、五右衛門が香椎宮・筥崎宮参拝の帰りに潮先において恵比須神の御尊像を拾い、翌、文禄元年 西暦1592年1月10日 社殿を営み、恵比須神を祀る。
十日恵比須神社創建。

どんな神様がいるの?
事代主大神(ことしろぬしのおおかみ)と大國主大神(おおくにぬしのおおかみ)の二柱をお祀りしています。
事代主大神は「えびす様」、大國主大神は「だいこく様」という呼び名で広く知れ渡っており、最も親しみのある神様です。

他のえびす神社とは違うの?
当社は事代主大神をお祀りしており、西宮神社のえびす様は蛭子神をお祀りしております。
このように、同じえびす様でもお祀りしている神様が違う場合があります。
又、当社には、えびす様(事代主大神)の父神、だいこく様
(大國主大神)も一緒にお祀りしております。
全国的にも非常に珍しく出雲大社から御分霊を迎えて合祀致しました。

正月大祭ってどんなお祭り?
正月三が日を過ぎて福博の街で最初に行われるお祭りです。
今年一年間の商売繁昌、家内安全、交通安全、漁業繁栄などを願う人々で大変賑わいます。

十日恵比須神社の歴史

| 天正19年 | 西暦1591年1月3日 | 武内家隠居五右衛門が香椎宮・筥崎宮参拝の帰りに潮先において恵比須神の御尊像を拾う。 |
| 文禄元年 | 西暦1592年1月10日 | 社殿を営み、恵比須神を祀る。十日恵比須神社創建。 |
| 天和元年 | 西暦1681年11月15日 | 四代目平十郎が、創建90年に当たり、祟福寺境内にご社殿を再建。 |
| 宝歴元年 | 西暦1751年5月15日 | 八代目平十郎が社殿建て替え、鳥居を建立。 |
| 文久3年 | 西暦1863年 | 社殿再建。記録に博多の流れ世話人の名前がある。 |
| 明治12年 | 西暦1879年 | 福岡県の指示で祟福寺境内から東公園にご遷座。記録には博多世話人の名前が多数あり。 |
| 明治36年 | 西暦1903年 | 世話人が石鳥居を奉納。 |
| 明治42年 | 西暦1909年 | 呉服商組合が手水舎・石灯篭・汐井台、高砂連が清道旗を奉納。 |
| 明治43年 | 西暦1910年 | 閑院宮御台臨の建物を購入し開運殿と名づけ御座を始める。 |
| 昭和4年 | 西暦1929年 | 現在地に遷座。 |
| 昭和27年 | 西暦1952年 | 正月大祭が1月9日から11日までとなる。 宝恵駕が始まる。 出雲大社より大國主大神の御分霊を勧請。 |
| 昭和29年 | 西暦1954年 | 正月大祭を8日から始める。開運御座再開。 |
| 昭和44年 | 西暦1969年 | 「宝恵駕」がかき手不足の為、中止となる。 |
| 昭和45年 | 西暦1970年 | 「宝恵駕」に代わり「かち詣」が始まる。 |
| 平成3年 | 西暦1991年 | 御鎮座400年祭 |
| 平成20年 | 西暦2008年 | 天皇陛下御即位20年を記念し、狛犬が奉納される。 |
| 平成29年 | 西暦2017年 | えびす裏参り増加のため、裏参道を整備。 |
| 平成30年 | 西暦2018年 | 参道石畳整備。 |
| 令和2年 | 西暦2020年 | 十一月 手水舎のめで鯛石像新調。 十二月 大しめ縄新調(十年毎) |